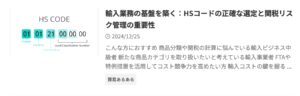こんな方におすすめ
- 初めての輸入通関に不安を感じている方
- 過去に輸入でトラブルを経験した方
- 通関業者とのやり取りが苦手な方
輸入ビジネスを進めるうえで、税関での通関手続きは避けて通れない重要なプロセスです。しかし、通関時に発生するトラブルは、初心者だけでなく経験者にとっても大きな壁となることがあります。特に申告外物品の発見や動植物検疫法違反の指摘、さらには通関業者との連携不足といった問題が頻発します。これらのトラブルは、ただ単に時間を浪費するだけでなく、事業全体に大きな影響を与えることも。
そこで本記事では、税関でよくある3つのトラブルとその具体的な回避方法について解説します。初心者の方はもちろん、トラブル経験がある輸入ビジネス経験者にも役立つ内容をお届けします。
目次
1. 申告外物品の発見とその影響
輸入通関時に最も避けたいトラブルのひとつが、「申告外物品」の発見です。輸入者は通常、商品が税関に到着する前に、申告内容を通関業者を通じて税関に提出します。この申告内容には、商品の名称、数量、価格、HSコード(関税番号)などが含まれており、税関はこれを元に通関手続きを進めます。しかし、商品の中に申告していない物品が含まれていた場合、その発見がトラブルの原因となるのです。
申告外物品とは?
申告外物品とは、輸入申告書に記載されていない物品のことです。たとえば、主商品とは別に、サンプル品、贈答用の品物、誤って梱包された部品などがこれに該当します。たとえば、パソコンを輸入する際に、付属品やサービス品が梱包されていた場合、それらが申告されていなければ申告外物品として扱われます。輸入者が意図せずに送り込まれた物品が申告漏れとなることもあります。
なぜ申告外物品が問題となるのか?
申告外物品が発見されると、税関はその品目が適正に申告されていないと見なし、取り扱いに問題があると判断することがあります。税関は、輸入申告書に記載された内容が正確であるかどうかをチェックしており、申告外物品が見つかると、以下のような問題が生じます。
- 関税や消費税の再計算
申告外物品が発見された場合、それに対する関税や消費税が再計算されることになります。もし未申告の物品に関税がかかるものであれば、輸入者は追加で税金を支払わなければならない場合があります。これにより、予想以上にコストがかかる可能性があります。 - 罰則や罰金の適用
申告外物品が意図的に隠されたものである場合、税関はそれを不正行為とみなすことがあり、最悪の場合、罰則や罰金が科される可能性もあります。これは輸入者にとって重大なリスクであり、場合によっては刑事責任を問われることもあります。過去に申告漏れがあった事例で、輸入者が商業的な利益を得るために意図的に隠匿した物品を発見され、重い処罰を受けたケースもあります。 - 商品の没収や返送
申告外物品が発見されると、税関はその品目が違法であるかどうかを調査します。もしその物品が輸入が許可されていないものであれば、最終的に商品が没収されたり、返送されたりすることがあります。特に規制品や危険物、または許可が必要な商材(例えば、医薬品や化学製品)が含まれていた場合、重大な結果を招くことになります。
私がフォワーダーに在籍していた当時、既存顧客の貨物でこのような事例はまず起きませんでした。というのは少し理由があって、そもそも輸入痛感には3パターンがあり簡単にいうと「すぐ許可、ちょい待ち許可、かなり待ち許可」に分かれるわけです。これについては以下の記事を参考にしてもらえると嬉しいです。
で、たまーにあるのが個人輸入(企業レベル含む)の一見さんで、自分で税関で手続きをする事ができないお客さんの書類が届くんです。担当がエリアで分かれていて、いつもルーティンワークの中で暇なら気分転換になるんですが月曜のくそ忙しい時にこういうお客さんが来るとまぁまぁウザいわけですよ。
で、そういう客に限って電話してきて「うちの荷物届いてませんか?」で病院のたらい回しよろしく自分が担当の場合はやり取りをします。インボイスを見ながら荷物の中身はどんなもので、材質は何で、とか目的も聞いたりします。まぁ、そういうのはいいとしてここからが問題なのですが、基本貿易をする業者は輸出入者符号をあてがわれていることが多いです。が、スポットのお客さんでこの番号を持っていることはまず無いので999999で手続きをするわけですが、こういう輸入貨物が即時許可されることは10000%ありません。書類審査か貨物検査になります。
で、話を戻すと貨物検査になってインボイスにないものが出てくると、「おいおい、これなんだ?」なんてこともしばしば。僕が経験した事例だと、海外からだと購入物以外にプレゼント的に別の商品を入れ込んでくることがあるんです。で、数が合わない、これなんだ。と。勿論購入した商品ではない証明(支払い明細)があれば、整合性が取れれば問題にはならないのですが、こちらからするとヤキモキしますしただでさえ忙しい時に税関へ行ったり、その客に説明したりして、てんてこ舞いになっていたのを思い出します。
申告外物品が発見された場合の影響
申告外物品が発見された場合、その影響は輸入ビジネスにとって非常に大きなものとなり得ます。まず、商品の通関が一時的にストップし、税関からの追加確認や指示を待つことになります。これにより、商品の納期が遅れるだけでなく、在庫管理や販売計画にも支障をきたします。
さらに、追加の関税や罰金が課せられた場合、利益を圧迫することになります。商品自体のコストや配送費用が上昇し、最終的には輸入者が予想していた利益を大きく減少させることになります。
申告外物品の発見は、輸入ビジネスにとって大きな障害となる可能性があります。しかし、事前にしっかりと準備し、チェック体制を整えることで、このようなトラブルを避けることができます。輸入者として、申告内容を正確に伝えることの重要性を再認識し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じることが求められます。
密輸品ではなくても「動植物検疫法」に違反する事例
輸入ビジネスを行っている場合、商品の品質や価格、流通経路に注目が集まりがちですが、実は「動植物検疫法」にも十分な注意が必要です。多くの輸入者は、輸入する商品が植物や動物に関連しているかどうかを見落としがちですが、意外にも多くの商品がこの法律に触れる可能性があります。ここでは、密輸品ではなくても、動植物検疫法に違反する可能性がある事例と、その対策について詳しく解説します。
動植物検疫法とは?
動植物検疫法は、日本における植物や動物の病害虫の防止を目的とした法律です。この法律のもと、輸入される物品の中で動植物由来の素材を含むものや、動植物に関連する製品は、検疫を受ける必要があります。主に農産物や動物の生体、植物の種子などが対象になりますが、意外にもこれら以外の製品にも影響を及ぼします。たとえば、木製品や皮革製品、ハーブやアロマオイルなどが検疫対象となる場合があります。
違反事例1: 木製品や木材を使用した商品
木材や木製品は、動植物検疫法において特に注意が必要なカテゴリーです。木材には、病害虫や有害な微生物が付着している可能性があり、適切に処理されていない場合、日本国内に病害虫を持ち込むリスクがあります。たとえば、家具や木製インテリア、木製のおもちゃ、楽器などが輸入される際、これらの木材が適切に処理されていないと、動植物検疫法に違反することになります。
特に輸入元で「熱処理」や「燻蒸(くんじょう)」といった防疫処置が施されていない場合、日本に到着後、税関での検査に引っかかる可能性があります。検査で不適合が見つかれば、商品の輸入が拒否されるか、最悪の場合には廃棄処分となることもあります。
違反事例2: 皮革製品や動物性製品
革製品や動物性素材を使用した商品も動植物検疫法の対象となることがあります。特に、動物由来の素材(皮革や毛皮、羽毛など)を使用した製品は、動物の病気や寄生虫を国内に持ち込む可能性があるため、十分な検疫を受ける必要があります。たとえば、革製のバッグや靴、衣料品、毛皮を使用したアクセサリーなどがこれに該当します。
これらの製品が輸入される際に、適切な検疫証明書や処理証明書が添付されていない場合、税関で発覚し、商品が引き戻されたり、消毒処理が施されたりすることがあります。また、動植物検疫法に基づき、動物性素材が使用された製品に対する検査が厳格に行われることもあるため、事前に確認を怠ると大きなトラブルを招きます。
違反事例3: ハーブやアロマオイル、化粧品
意外かもしれませんが、ハーブやアロマオイルも動植物検疫法に引っかかることがあります。これらは植物由来の製品であり、輸入時に病害虫や微生物が付着している可能性があるため、検疫を受ける必要があります。特に、植物性のオイルやエキスを使用した製品が多い化粧品や健康食品は、動植物検疫法の対象となる場合があります。
輸入する際には、植物が栽培された地域や生産過程で適切な管理が行われているかを確認することが大切です。もし、輸入時に証明書が不足していたり、不正な処理が行われていた場合、税関で差し止められ、追加の手続きや費用が発生することがあります。
動植物検疫法に違反した場合の影響
動植物検疫法に違反すると、以下のような影響を受ける可能性があります:
- 商品の返送または廃棄
検疫基準を満たしていない場合、商品の輸入が認められず、輸入した商品が返送されたり、廃棄されたりすることがあります。これには輸送費や廃棄費用がかかり、輸入者にとって大きな経済的損失となります。 - 追加の費用
検疫処理が必要と判断された場合、輸入者は消毒費用や検査費用を負担することがあります。これらの費用は予期していなかった追加コストとなり、商品の利益率を圧迫する可能性があります。 - ブランドの信頼失墜
動植物検疫法に違反した事例が報道されることによって、ブランドや企業の信頼が失われることもあります。特に消費者の安全や健康に関連する商品であれば、その影響は長期的に続くことがあります。
動植物検疫系は国内の生態系を狂わす恐れがあるので軽微なレベルな話ではないですよね。で、意外なのが製品だけではなくて梱包物もその対象とされている(当たり前と言えばそうなのですが。)点で、木材に未確認の虫がついている可能性があるという事件が以前発生した際は、該当国からの貨物のコンテナを全て燻蒸、場合によっては滅却処理をする状況が発生していました。
水際で国内の危機を防ぐとはまさにこのことだと思います。
通関業者との連携と正確な情報提供の重要性
通関業者の役割
通関業者は、輸入者に代わって税関との間で必要な手続きを行い、貨物が日本に到着するまでの一連の流れを管理します。彼らの主な業務は、輸入申告、関税や消費税の支払い、必要な書類の提出、そして商品の検査対応です。通関業者は、法律に基づいた通関手続きを確実に行うため、輸入者が遵守すべき規制や税率、書類提出期限を熟知しており、その知識を基に正確に手続きを進めます。
連携不足のリスク
通関業者との連携がうまくいかない場合、以下のような問題が発生することがあります:
- 手続きの遅延
通関業者との情報共有が不十分だと、必要な書類が欠落していたり、税関に提出する内容が誤っていたりすることがあります。これにより、通関手続きが遅延し、商品の到着が遅れる可能性があります。遅延が発生すれば、販売計画や在庫管理に大きな影響を与えるため、企業の業務運営に支障をきたすことになります。 - 誤った関税の支払い
輸入者が提供する商品情報が不正確だと、通関業者が誤った税額を計算することがあります。関税や消費税の額は商品やその原産地に応じて異なるため、誤った情報に基づいて過剰に支払ってしまう場合もあります。これを後から修正するには時間と費用がかかり、場合によっては過剰に支払った税金の返還手続きも必要となります。 - 違法な輸入のリスク
提供する商品情報が不正確な場合、通関業者が誤った分類(HSコード)で申告することもあります。この場合、商品が規制品として扱われることがあり、税関で差し止められることがあります。また、薬事法や動植物検疫法など、輸入規制に違反するリスクも高まります。これにより、商品が返送されたり、廃棄されることがあり、最悪の場合、輸入者に法的な責任が問われることもあります。
正確な情報提供の重要性
通関業者と円滑に連携するためには、正確で詳細な情報を提供することが不可欠です。特に以下の点に注意することが重要です。
- 商品内容の正確な記載
輸入する商品の内容や仕様、材料についての詳細な情報を通関業者に提供することが重要です。これには、商品の名称、使用目的、原産地、成分、数量、重量、HSコードなどの情報が含まれます。正確な情報を基に通関業者が適切な申告を行うことで、関税の適用や通関手続きがスムーズに進みます。 - 関税分類の確認
商品ごとに適切なHSコード(関税分類番号)が設定されているかを確認することも大切です。誤ったHSコードを申告すると、関税率が異なることがあるため、最適なコードを選定し、通関業者に正確に伝える必要があります。また、商品が規制品に該当する場合は、必要な許可証や証明書を事前に取得しておくことも重要です。 - 必要書類の準備
通関業者が必要とする書類(インボイス、パッキングリスト、輸出証明書など)を事前に準備して提供することがスムーズな通関に繋がります。特に、商品の検査や規制に関連する書類が必要な場合、その準備が遅れると、検査が長引き、商品の到着が遅れる可能性があります。 - 定期的な情報共有
通関業者とは定期的に情報を共有し、最新の輸入規制や法改正、手続きに関するアップデートを把握しておくことが大切です。特に、輸入国の法律や規制は頻繁に変更されることがあり、これを見逃すと不適切な手続きが行われ、最終的にトラブルを招く原因となります。
ここはまさに私の経験談が生きるんですが、ぶっちゃけ声を大にして言います。通関業者を下にみる顧客が多すぎる。電話越しの対応もそう、メールの文面もそう、同僚もみんな言ってました。『「できて当たり前」って思われるからこんな風に上から目線で来られるけどオタクらの不備やらもこっちが責任負うこともあるし、なんかなぁ。』なんて。
もちろん、我々がサービスを提供する立場なわけですので下手に出るのは当然のことです。態度が横柄なのもグッと堪えます。でもね、こっちも人間です。「これをお願いします。」とか「この部分、不明確で教えてください。」等電話メール問わず質問をすると。「はぁ?面倒だなぁ。」「適当にやっといてよ。」とかそんなリアクションをされると「はぁ。」という気分にならない方が難しいですよね?
こちらも仕事です。若手ということもありこちら側の質問の仕方に不測があったりとか落ち度もゼロとは思いませんが、少なくとも提供してもらわないといけない情報がないと前に進まないのにそれが滞るとかほんま地獄です苦笑
ですので、輸入者側が通関業者に不満を持つ場合、無意識に痛感業者に対して高圧的になっている場合が往々にしてある、と思ってもらう位がちょうど良いと本当に思います。一度経験してみたら良いと思います、輸入通関って考えているよりよほど煩雑ですよ
まとめ
輸入ビジネスにおける税関でのトラブルは、計画通りの事業運営を妨げる大きな要因となり得ます。しかし、事前の準備と適切な対応策を講じることで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。この記事では、「申告外物品の発見」、「動植物検疫法への違反」、「通関業者との連携不足」に焦点を当て、それぞれの問題点と具体的な回避策を解説しました。
重要なのは、輸入商品に関する正確な情報を把握し、それを通関業者や税関に適切に伝えることです。また、輸入規制や必要な書類について最新情報を常に確認する姿勢も欠かせません。さらに、信頼できる通関業者との良好な連携は、輸入プロセス全体の効率化に繋がります。
輸入手続きには複雑な要素が多いですが、適切な準備と対応によってリスクを最小限に抑えることが可能です。本記事の内容を参考に、よりスムーズで安全な輸入ビジネスを行ってください。